ClientEarth
2025年3月5日
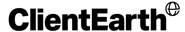

山下朝陽、 ハナ・ハイネケン(ClientEarth)著
2025年3月5日 NIKKEI GX
政府が発行するGX(グリーントランスフォメーション)経済移行債(クライメート・トランジション利付国債)は、累計3兆円程度に達した。初めて発行した1年前は通常の国債より利回りが低くなる「グリーニアム(緑のプレミアム)」がみられたが、足元では消滅し、投資家が好んで保有する銘柄でないことを示している。資金が水素やアンモニアなどの支援に使われ、海外投資家は化石燃料関連資産を長期で維持・延命させる「カーボンロックイン」になるとの懸念を持っている。
3割を日銀が保有
政府は、50年にカーボンニュートラルを実現するため、公的資金を20兆円、民間資金と合わせると総額150兆円を投入する目標を掲げる。GX移行債はその財源となる。2024年2月に初めて発行し、今年1月まで6回発行した。発行済みのGX移行債のうち、3割程度は日本銀行が保有している。
関連省庁の基本方針によると、資金使途には再生可能エネルギーの主力化、蓄電池産業への投資、海底直流送電等の整備などが含まれる。ただ水素・アンモニアやガス市場の整備、二酸化炭素を回収・貯留・再利用(CCUS)など、グリーンではない使途も多い。とりわけ電力など炭素高排出セクターで水素・アンモニアを混焼することへの懸念が大きい。
一般論として、炭素排出のない生産設備に移行するには巨額の設備投資が必要で、この動きを支援するトランジション・ファイナンスは強く推進しなければならない。ただ炭素高排出の事業や生産設備の場合、脱炭素社会への移行に向け、パリ協定の気温目標や目標達成への道筋に沿う必要がある。炭素高排出産業への資金支援は、化石燃料関連資産を延命させるカーボンロックインになりかねない。
そこで「科学的に信頼性ある移行であるか」「移行の軌道を外れていないか」の2点が厳しく問われる。国家と事業主がパリ協定に沿った移行計画を持つことが不可欠だ。もし炭素をほぼ排出しない設備を実現できるのであれば、その設備を導入する。それが難しく化石燃料を使う設備を維持せざるを得ない場合は、廃止する期限「フェーズアウトデイト」を示す必要がある。
ブルー水素、脱炭素に逆行の場合も
また発電、製鉄といったサプライチェーン(供給網)の一部分だけに焦点を当てて脱炭素を目指すのは無責任である。採掘や輸送、製造、利用といった製品のライフサイクル全体で炭素排出を削減するものでなければならない。ライフサイクルで炭素排出を増やすようではトランジション・ファイナンスと言えない。
例えば水素・アンモニアはどのように作られたか、ライフサイクルの炭素排出を考慮しなければならない。 現状では大半が化石燃料に由来するため、国際エネルギー機関(IEA)の委託研究の報告書で は気候変動の解決策というより、むしろ気候変動の原因と指摘している。
化石資源から水素を製造する過程でCO2の回収・貯留(CCS)を付設する場合はブルー水素と呼ばれる。しかしCCSには、運搬や貯留場所など技術的・経済的な課題があり、回収・貯留されるCO2の比率は100%には程遠い。さらにCCSの設備稼働に必要な化石燃料に加え、化石燃料を採掘するときにメタンが漏洩することも考慮しなければならない。電力部門でブルー水素を使った場合、天然ガスよりライフサイクル排出量が多い場合があると複数の研究者が明らかにしている。
アンモニア・合成メタンにも懸念
アンモニアの脱炭素は、水素よりもハードルが高い。アンモニアの多くは天然ガスから作られ、ハーバーボッシュ法という高温高圧のプロセスを経るため、製造工程で多くのエネルギーを必要とする。
CO2を大気に排出した場合はグレーアンモニア、CCSを付設する場合はブルーアンモニアと呼ばれる。どちらも天然ガス採掘時にメタンが漏れたり、アンモニア燃焼時に温暖化係数がCO2の約300倍とされる一酸化二窒素(N2O)を排出したりするリスクがあるため、ライフサイクルの炭素排出は少なくない。
経済産業省がガス分野の技術 ロードマップで導入を目指す合成メタンにも同様の問題がある。合成メタンは水素とCO2から作られ、炭素排出をどのくらい減らせるのかという課題に加え、ガスインフラを拡大する点も懸念される。
液化天然ガス(LNG)は燃焼時だけではなく、上流の採掘時や輸送時のメタンガス漏れの影響で、ライフサイクルのCO2排出量は非常に大きい。例えば米国が輸出するLNGの温暖化効果は石炭の3割以上多いと言われ、トランプ新政権のもとでは現状を維持するか、場合によっては悪化する可能性が十分にある。
資金使途の見直し欠かせず
ガスインフラの拡大や石炭火力発電所でのアンモニア混焼、ガス火力での水素混焼はカーボンロックインの懸念が大きい。製鉄所の高炉に水素を注入する技術に関しても、石炭を使う高炉製鉄を存続させるカーボンロックインになる可能性がある。
GX移行債が、真のトランジション・ファイナンスと見なされるためには、カーボンロックインにつながったり、ライフサイクルでの炭素排出を増やしたりする技術には資金を支援しないという原則が必要になるだろう。さらに科学的な根拠に厳格に照らし、パリ協定に整合した排出削減パスウェイに基づいて支援対象を選ぶ必要がある。
たしかに経産省は炭素高排出セクターに関して脱炭素移行のロードマップを示しているが、ライフサイクルでの炭素排出を考慮していない。ライフサイクルでの炭素排出を含め、最新の科学的見地からパリ協定に整合するようにロードマップを改訂する必要がある。
また一定の炭素高排出の設備については法令で廃止期限のフェーズアウトデイトを定めた上で、より早期に廃止する場合に支援を提供する一方、削減違反の場合には支援を返還するといった仕組みも取り入れるべきである。
この記事は、日経GXに掲載されたもので、許可を得て転載しています。
本記事の英訳版はこちらから参照できます